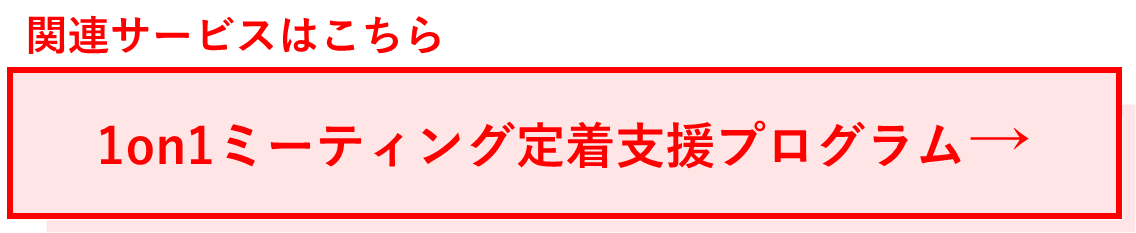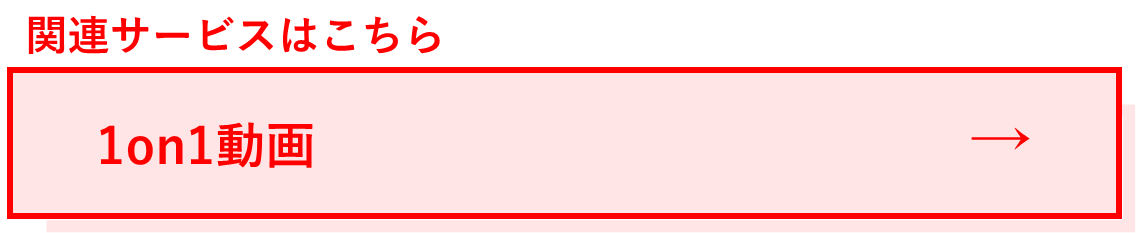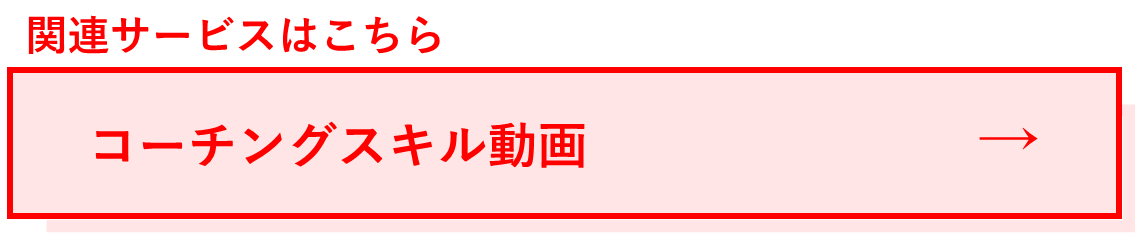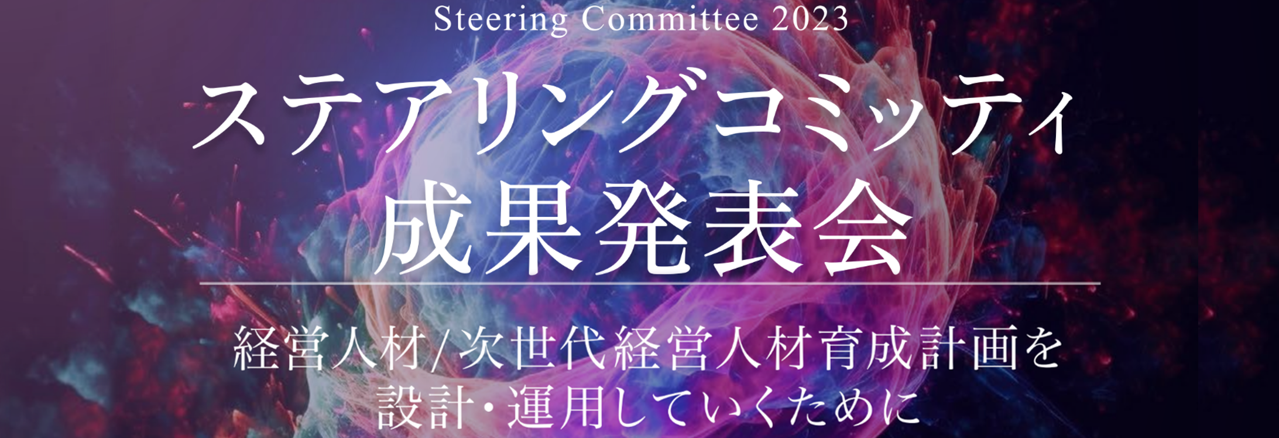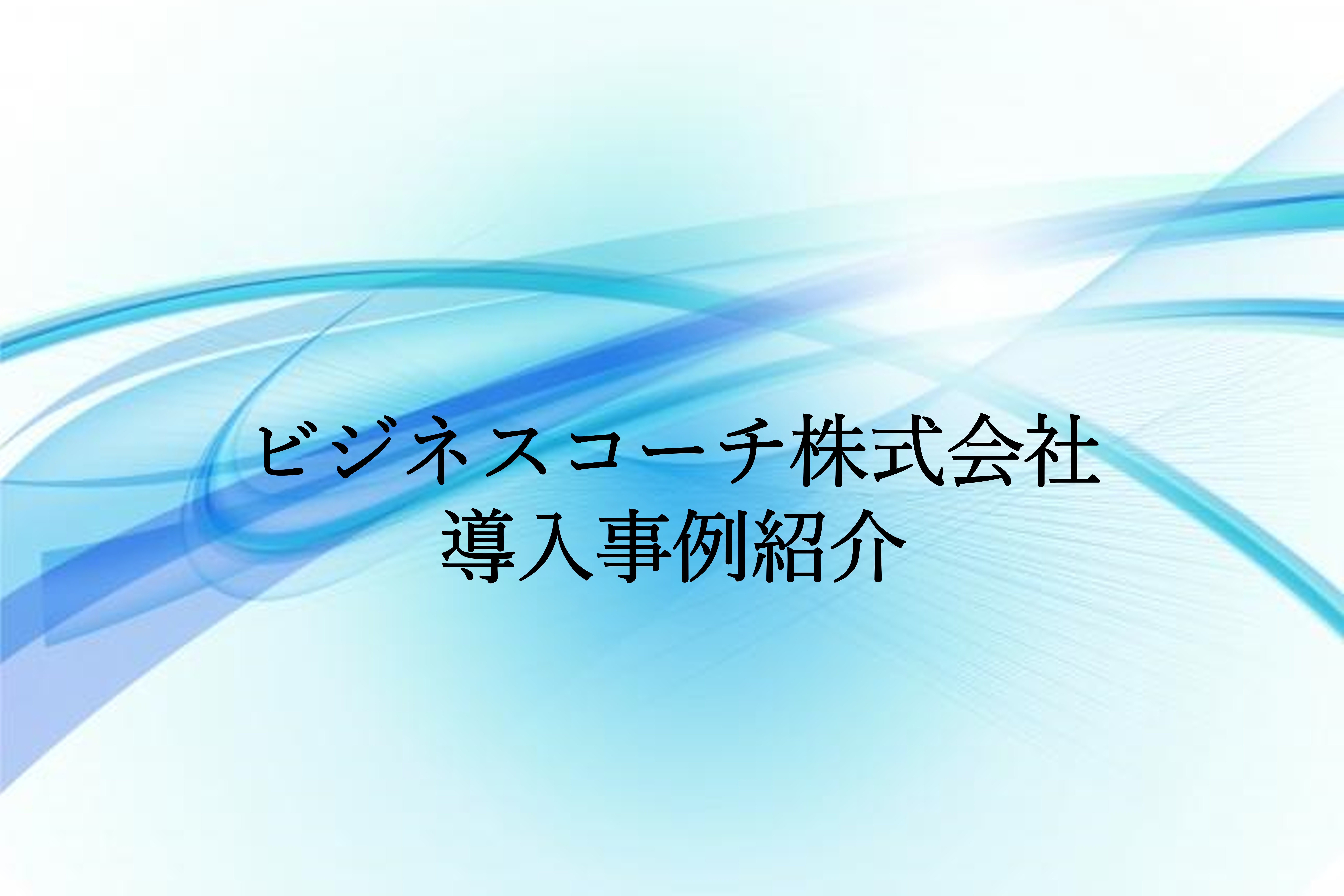- 1on1ミーティング定着支援プログラム
- 1on1動画
- コーチングスキル動画
クオリサイトテクノロジーズ株式会社
1on1ミーティング導入プログラム
「ナナメ」「ヨコ」「非公式」に広がるコミュニケーション。1on1導入はリーダー人材育成にもつながった

左から、クオリサイトテクノロジーズ株式会社 コーポレートマネジメント部 部長 晒谷 健史 氏
コーポレートマネジメント部 人財開発グループ 伊佐 ゆかり 氏
コーポレートマネジメント部 人財開発グループ 課長 江川 貴代 氏
企業の成長を大きく左右するリーダー人材の育成。その好事例として注目したい企業が、沖縄と北海道を起点にしたニアショア開発で事業拡大を続けるクオリサイトテクノロジーズ株式会社です。同社では1on1を導入することでマネジメントの型をつくり、上司・部下の間だけでなく「ナナメ」「ヨコ」など組織横断でのコミュニケーション活性化を実現。1on1を効果的に進めるための知見は若手メンバーにも共有され、将来を担うリーダー候補人材の成長にもつながっています。
クライアント企業情報
クオリサイトテクノロジーズ株式会社
ニアショアに特化したシステム開発・運用、データセンターを運営。
資本金:1億円。
売上高:23億6156万円(2022年度実績)。
従業員数:220名(2023年4月現在)。
ご担当者様
コーポレートマネジメント部 部長 晒谷 健史 氏
コーポレートマネジメント部 人財開発グループ 伊佐 ゆかり 氏
コーポレートマネジメント部 人財開発グループ 課長 江川 貴代 氏
お客様の課題・ご要望
30歳前後でのキャリア入社の管理職が多く、その後モデリングできる上司が不在の環境下において働いてこられた中で、各自が自己流のマネジメント手法にて組織管理をしてきた結果、今後の事業成長のネガティブリスクとして若手の離職等が懸念される状況。
ビジネスコーチの提案・サポート
1on1ミーティング導入プログラム
管理職が自身の組織における役割期待を理解したうえで、管理職としてのあるべき姿を認識し、行動変革の必要性に気づいていただくとともに、それらの実践に向けたマネジメントスキル(※)の習得を目指す。その対話のカギとなる仕組みとして1on1の導入をご提案。
※特に、対話において必要となる共感力をベースとしたコミュニケーション力
「マネジメントの型」を共有するために1on1を導入
——1on1を導入した背景についてお聞かせください。
晒谷:導入を検討し始めたのは2018年です。当時は創業13年、社員数はまだ200人に満たない頃でしたが、事業成長とともに組織規模も拡大し続けていました。一方で管理職の数は非常に少なく、それぞれプレイングマネージャーの側面が強いこともあって、メンバーをマネジメントしきれていないのではないかと感じる場面も増えていました。
そんなときに親会社出身の監査役から「以前に別企業で導入した1on1が効果的だった」と聞き、一人ひとりの社員と向き合う手法に興味を持ったのです。
——導入プロジェクトにおいては、当初から全管理職を対象にしていますね。
晒谷:はい、全部門の全管理職を対象としてプロジェクトをスタートさせました。
当時の管理職はマネジメントのロールモデルもない中で、それぞれが我流のやり方で必死に頑張っている状況でした。せっかく1on1を導入するのであれば、メンバーとの正しい向き合い方を学び、全管理職で「マネジメントの型」を共有したいと考えたのです。
——具体的なプロジェクトの流れについて教えてください。
晒谷:管理職はまずビジネスコーチの座学研修を受けて、1on1の基本的な知識を学びました。さらにプロコーチをお招きし、管理職自身がコーチングを受ける機会を設けました。
私も研修に参加し、コーチングを受講したひとりです。研修では「傾聴」や1on1の「7 STEP」などの具体的な手法を学ぶことができました。プロコーチとの会話では私の中にある本音を深く引き出していただき、話したことで自分の考えが整理されたり、次のアクションが明確になったりして、すっきりする感覚がありましたね。1on1の意義をまざまざと体感しました。
並行してメンバー側にもビジネスコーチの動画教材で「1on1とは何か」を学んでもらい、実際の職場での1on1をスタートさせました。
傾聴の難しさを実感しながらメンバーの思いを引き出す
——職場での1on1はどのような形で行っているのでしょうか。
江川:私がメンバーと行っている1on1についてご紹介しますね。
私自身は2022年に管理職になったばかりで、まずはメンバーとの関係構築を重視していました。1on1の時間は「メンバーのための時間」であることを強く意識し、メンバーの成長に何らかの形でプラスとなるようにしたいと思っていました。そこでメンバーとは「1on1をどんな時間にしていきたいか」を話し合い、個々に合ったテーマを設定しています。
関係構築の面では、私自身がコーチングを受けて印象に残った「傾聴」を重視しています。相手の話を丁寧に聞こうとしているかどうかは、態度や言動に表れるもの。その学びをもとに、メンバーの話を興味を持って聞くとともに、相手がどうしていきたいのか、何を望んでいるのかを想像しつつ、答えをあくまでもメンバーに出してもらうことを意識しています。
実際にやってみると、傾聴は想像していた以上に難しかったですね。「私だったらこうするよ」と言ってしまいそうになるのを押しとどめて、メンバーの中にある答えを引き出せるよう努めているところです。
——他社では「1on1を何度かくり返していると話すネタがなくなる」と悩んでいる管理職も多いようですが、江川さんはいかがでしょうか。
江川:その悩みはよく分かります。私も1on1の回数を重ねていくうちに、メンバーからテーマが出てこなくなったことがありました。そんなときは、こちらから話題を投げかけることもあります。日々のメンバーの様子を見ていて印象的だった行動があれば、「あのときはなぜこの行動を取ることができたんですか?」「どんな思いがあって取り組んだんですか?」といった形で質問していますね。
良い行動の背景にある思いを本人の言葉で振り返ってもらうことで、何かしらキャリアのプラスになるのではないかと考えています。
——1on1を実施するようになってから、職場にはどのような変化が見られますか?
晒谷:全体の傾向を調べるため、導入後の最初の1年はアンケートを取って1on1実施後の変化を測定しました。1on1の取り組みについては、満足度が高く、ポジティブな声が多い結果となりましたね。
それ以外にも、当社では年1回の社員満足度調査を実施しており、1on1導入後は初年度から、上司に関する項目や仕事・商品に関する項目など、ほぼすべてのポイントが上昇しています。この背景には、1on1によって働き方や人事制度について話す機会が増え、会社の取り組みに対する理解が深まったことがあるのではないかと考えています。
リーダー人材の育成にもつながる「ナナメ1on1」の効用
——1on1の取り組みを形骸化させないために工夫していることはありますか?
晒谷:ビジネスコーチによる管理職向けのフォローアップ研修を3年連続で行っています。フォローアップを続けているのは、基礎に立ち返る機会をつくるため。1on1をくり返していると、いつしか我流のやり方になってしまうこともありますから。
ビジネスコーチの皆さんは、こうしたフォローアップの流れも含めて当社のためにカスタマイズし、仕組みに落とし込むサポートをしてくれるため、とても助かっています。このサポート体制が、ビジネスコーチを3年以上継続して利用しているひとつの理由ですね。
フォローアップ研修を受けた管理職は、他の管理職の取り組み事例を聞いたり、新しいコーチング理論を学んだりして刺激を受けているようです。プロコーチによる個別セッションも、管理職1人につき30分×3回まで受けられるようにしています。
——自身の1on1のあり方を振り返り、アップデートする機会になっているのですね。
伊佐:はい。プロコーチのセッションを受ける中では「業務上の直接的な利害関係のない人との1on1」がとても有意義だという発見もありました。これがヒントとなって、現在は「ナナメ1on1」にも取り組んでいます。
「ナナメ1on1」は新入社員と2年目社員を対象とし、別部署に所属する入社5年目くらいまでの先輩社員がメンターとなって1on1を実施する取り組みです。私は先輩社員となるメンターを取りまとめる事務局を担当しています。
普段の業務ではほとんど関わることのない者同士が1on1を行うことで、上司との1on1とは違った形で本音が出てくることもあります。部署を超えた社内コネクションが生まれることも、若手メンバーにとっては心強いのではないでしょうか。
——ナナメ1on1を運用したことで、新たな発見や気づきはありましたか?
伊佐:先ほど江川の話にあった「1on1で話すネタがなくなってしまう」という悩みを、どのメンターからも聞くようになりました。そんなときは、どんなふうに後輩と会話していくべきなのか管理職に相談させてもらい、引き出し方などの手法を学んでいます。
晒谷:メンターを務めることは、「プレ管理職」の経験を積むことでもあるんですよね。メンターには将来的なリーダー候補人材を指名しているので、1on1の意義や手法を学びながら、管理職の視点を身につけていってほしいと考えています。
「ヨコ」「非公式」にも広がるコミュニケーション
——お話を伺って、貴社ではコミュニケーションそのものの価値が大きく見直され、以前よりもずっと重視されるようになったのだと感じました。
伊佐:限られた業務時間の中で会話の時間を捻出し、課題解決の目的意識を持ってコミュニケーションを取る習慣ができたことは大きな変化だと思います。ランチをしながら、一緒に歩きながらなど、さまざまなシチュエーションで実行できるのが1on1の良さですよね。最近では、普段は接点のない相手や、役職がかなり上の人などに「1on1をお願いできますか?」とお願いする「非公式1on1」も盛んに行われています。
江川:私の場合は、自主的に管理職同士の「ヨコ1on1」を行っています。フォローアップ研修の場以外でも管理職同士で話し、課題感や悩みを共有することで、新しい知恵をもらえることが多いんです。以前はひとりで悩むことも多く、メンバーにも相談できずに困っていた時期もありました。1on1が定着したことで、そうした悩みや不安が払拭されました。
——1on1が定着した現時点だからこそ感じる課題はありますか?
晒谷:「ナナメ」や「ヨコ」、あるいは「非公式」など、さまざまなレイヤーでコミュニケーションが活性化したことには大きな手応えを感じています。
ただ、これまでの取り組みはどちらかというと不満足の解消がアクションのメインになっていたようにも思います。今後はさらに1on1の質を高め、より建設的な会話ができる場にしていきたいですね。社員の成長にコミットするという目的に向かって、1on1以外にも有効な手法があれば積極的に検討していきたいと考えています。 写真提供:クオリサイトテクノロジーズ株式会社
写真提供:クオリサイトテクノロジーズ株式会社