連載コラム「CHRO対談」第3弾:アルプスアルパイン株式会社
組織・経営に関わる人に向けた連載コラム
-
CHRO対談
 創業者の想い「人に賭ける」を再定義して人事の進化を加速。
創業者の想い「人に賭ける」を再定義して人事の進化を加速。
「革新的T型企業」への変革で更なる躍進を目指す
HRエグゼクティブコンソーシアム 代表 楠田祐氏の協力のもと企画された本対談では、採用や育成、評価、働き方改革、人的資本経営、DE&Iなど、企業の人事戦略・変革に関わるテーマを扱い、ビジネスコーチ株式会社エグゼクティブコーチ本部・部長の出口がさまざまな企業の経営者や人事部門の担当者と対談を実施。企業の経営者や管理職、経営企画、人事・教育などの組織・経営の業務に従事している方へ向けて、日ごろの業務やこれからの戦略策定におけるヒントをお届けします。
***
76年の歴史をもつグローバル企業、アルプスアルパイン株式会社。「人に賭ける」の創業者の想いで築いた「人」を強みに、町工場から売上1兆円を伺うまでの大企業へと発展してきました。しかしその道のりでは、厳しい経営環境から効率優先となり、人財育成が形式化してしまうこともありました。現在は、目指す姿である「革新的T型企業」を実現するため、人事制度改革と組織融合を積極的に進めています。その実態と展望について、人事部長の池松裕史氏に伺いました。
執筆者

【プロフィール情報】
アルプスアルパイン株式会社
人事部 部長 池松裕史(いけまつ・ひろし)

ビジネスコーチ株式会社
エグゼクティブコーチ本部 部長
出口亮輔(でぐち・りょうすけ)

ファシリテーター:
HRエグゼクティブコンソーシアム
代表 楠田祐(くすだ・ゆう)
「革新的T型企業」を目指して経営統合し、ハードとソフトの融合で差別化を図る
楠田:本日は、2019年のアルプス社とアルパイン社の経営統合と「革新的T型企業」戦略、そして更なる躍進を目指す現在・将来の人事施策についてお話いただきたいと思います。
出口:最初に、御社の沿革を教えていただけますか。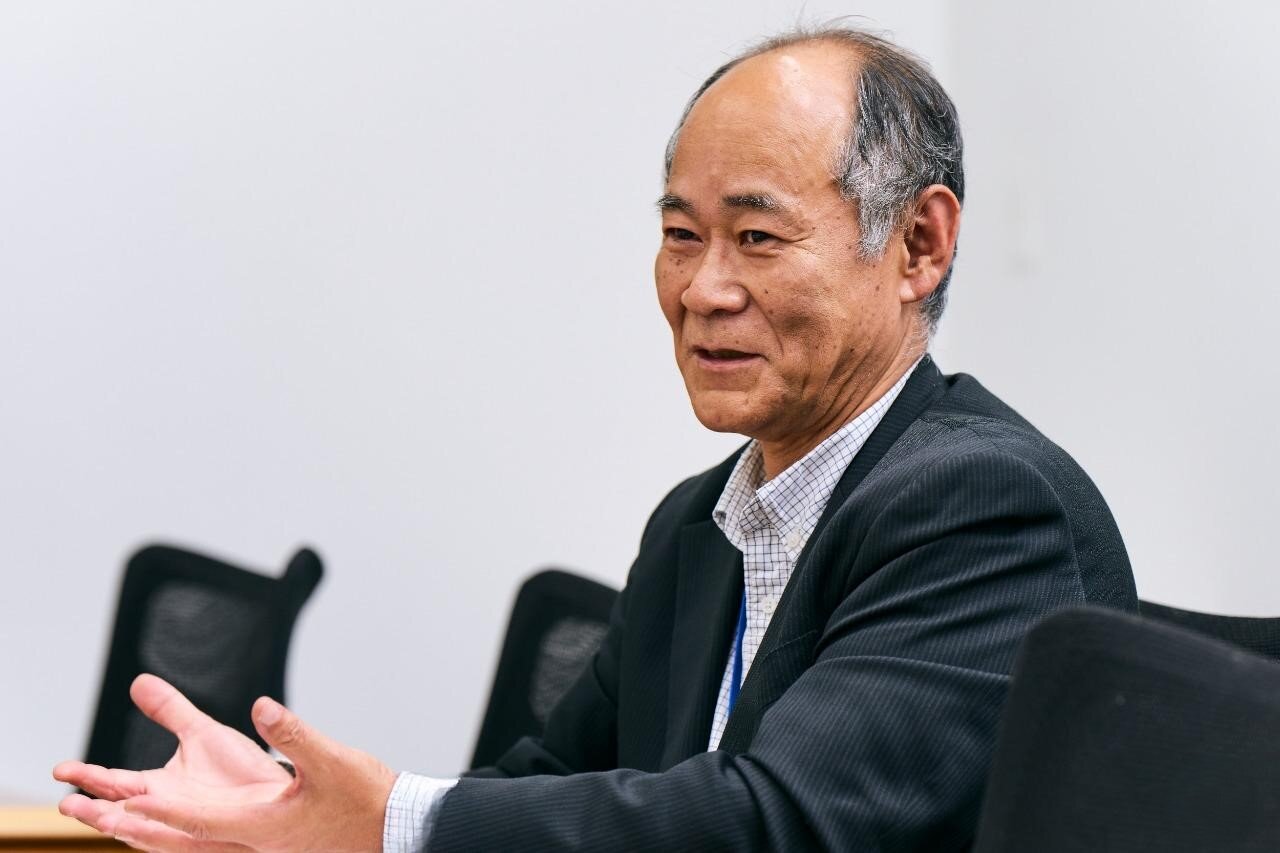
池松:アルプス電気は1948年、東京・大田区で部品メーカーとして創業しました。本社のこの場所が創業の地です。ロータリースイッチから始まり、テレビ用のチューナーで業務を拡大して輸出を開始しました。1960年代には車載セットメーカーとして、モトローラ社との合弁会社、アルプスモトローラ(後のアルパイン)を設立。その後OA機器、光通信機器やカーナビといったデジタル機器、PC関連製品へと発展し、2000年代にはデジタルメディア関連、2010年代にスマートフォン関連に展開しています。そして2019年にアルプス、アルパインを統合し、アルプスアルパインとして今日に至っています。
出口:2019年の経営統合で目指していたのが、「革新的T型企業」とお聞きしています。これはどういうことなのですか。
池松: 2万品目もの部品を開発製造する技術力(ハード)のアルプス、外部調達によりカーナビなどの車載完成品を製造するシステムインテグレーション力(ソフト)のアルパイン、その両社の力を統合することで、ハードとソフトを融合する。そしてシステム全体(Tの横線)と、技術を深耕した部品(Tの縦線)を組み合わせて、顧客がまだ気づいていない新しい価値を提案するのが「革新的T型企業」です。ハードとソフトを融合させることで他社には中身がわからない「ブラックボックス」化することにより、これまで以上の差別化を図る狙いもあります。
出口:なるほど、良くわかりました。素晴らしい戦略ですね。経営統合から5年経って、そうしたシナジー効果は出ていますでしょうか。
池松:ちょうどコロナ禍やウクライナ情勢と重なってしまい、物流コストの増大や半導体不足、部品原価とエネルギーコストの高騰などが降りかかりました。数字的にはこれから効果が見えてくると期待しています。
出口:経営統合後に、一番ご苦労されたのはどのような点ですか。
池松:「ワン・アルプスアルパイン」を掲げて融合を図りました。ただ、資本面でアルプスがアルパインを吸収したこともあり、アルプスのやり方に合わせる動きがありました。アルパインが築いてきた組織文化や業務プロセスは、顧客との関係の中からビジネスに最適化して生まれ、育まれてきたもの。それをアルプスに合わせてください、とすることはもの凄く大変でした。技術力で部品を開発製造するアルプスの組織文化と、調達してインテグレーション力で完成品を製造するアルパインの文化は、想像以上に異なるものだったのです。基幹システム(ERP)も導入した時期の違いから別々のものだったので、アルプス側に寄せたらアルパインでは使えなくなることも発生して、大変苦労しました。
出口:5年かけて、そうした異なる組織文化を融合させたのですね。
池松:そうです。一旦、すべてを1つにまとめました。しかし現場ビジネスの実態から、この点は元のやり方の方がよいと判断されることも出てきて、今はアジャストしている最中です。
楠田:次の時代を見定めながら、選択と集中によって技術力とマネジメント力を極めてきた両社が統合してT型企業を目指している。元々グループ会社同士と言えども、その統合は一筋縄ではいかないご苦労があるのですね。
創業者の想い「人に賭ける」を再定義し、ベンチャーマインドをもった組織へ
楠田:本社社屋から徒歩数分のところに、研修センターがあります。新しい建物のようにお見受けしましたが、最近建てられたのですか。
池松:創業者、片岡勝太郎の想いは「人に賭ける」です。研修センターは創業20周年の1968年に設置され、2018年に建て替えられました。研修センターの扉には、片岡勝太郎の「企業はつぶれやすい しかし企業が瓦解しても、個人がつぶれるわけにはいかない。自らの『売り物』を堂々と主張できる人間を生み出すために、この道場は常に扉を開く」という言葉が記されています。
出口:創業当初から人的資本経営を実践されていたのですね。
池松:そう言えると思います。部品会社がこうした研修センターを設置することは当時は珍しかったですし、人材育成は創業以来、経営の柱になっています。
出口:研修センターでは、どのような研修を行っているのですか。
池松:主にマネジメント研修など、対面効果が期待される研修を行っています。国内には6拠点、世界では23か国、186の拠点がありますので、技術系研修やダイバーシティ研修、リスキリング研修などは、ビデオを使ったオンデマンド研修に切り替えて実施しています。
出口:創業の精神を継承しながら、研修の仕方も進化しているんですね。ところで池松さんは人事が長いのですか。
池松:いいえ、経営企画から2022年に人事に来ました。ですから日々勉強しながら改革を進めているところです。
出口:現在、力をいれて改革されているのはどのようなことですか。
池松:弊社は元々「人に賭ける」が特徴であり強みでしたが、ここ数年、経営環境が厳しかったこともあり、一部で形式化してしまったところもありました。創業者が残してくれた「人に賭ける」という大切な価値を復活させ、再定義して実践することが私の役目だと考えています。
「人に賭ける」の精神を社員制度の基本理念として具現化したものが「人間性の尊重」「集団精鋭」「自己啓発」の3つです。これを今風に言うと、「人間性尊重」は人権、一人一人の強みを活かす、LGBTQ+を含むダイバーシティ。「集団精鋭」は2つあって、自分の『売り物』を作り競いあう中で互いに切磋琢磨する、もう一つが社員全員の強みを繋げた組織力。「自己啓発」は自分で自分の価値を高めるキャリア自律、と言い換えられると考えています。
出口:創業からの基本理念は、時代を経て言葉が変わっても、その真髄は変わっていないのですね。
池松:そうなんです。こうした基本理念に基づいて「目指す組織の姿」を定義しました。
・年齢を問わず、役割行動・組織貢献ができる人財が活躍し、評価されている
・個人(スキル・経験・行動様式)の多様性を活かし、組織能力が最大化されている
・個人が自律的にキャリアを描き、個人の成長とともに組織・事業が成長している
そして「目指す姿」の実現のために、職能型から役割型への人事制度改革を段階的に進めています。一般職から企画職への転換も可能にしましたし、今年は役職定年制を廃止しました。
出口:それは思い切った施策をされましたね。逆に言うと、現在は目指す姿ではない面があるのですか。
池松:残念ながら、それは否めません。人財・価値観の同質性が高く、効率性重視で上意下達のマイクロマネジメント。部品メーカーの特質として、決められたことをきっちりやることは強みでもあります。けれども、時代の変化にあわせてチャレンジしていくためには、大企業病を払拭して、ベンチャーメンタリティをもった組織へと変革を進めていく必要があると考え、これらの改革を進めています。
女性社員・女性管理職比率の向上施策を通して、誰もが働きやすい企業へ
楠田:ダイバーシティ&インクルージョンの一環として、女性社員、女性管理職についてお伺いできますか。
池松:女性採用は2000年代から積極的に行っていて、当時は女性総合職採用比率が2割ありました。ところが政府の働きかけなどで他社も力を入れてきて、2020年ごろの女性総合職採用は1割以下。採り負けてしまっていました。そこで2年前から、本業以外の業務を20%やってよいという「20%ルール」を活用して、技術職の若手女性社員に採用を手伝ってもらうことにしました。
出口:それは良いアイデアですね。成果は出ましたか。
池松:はい、今年は15%まで改善しました。女性のソフトウェアエンジニアや生産技術エンジニアが、応募してくださる学生さんに仕事の醍醐味や喜びを直接説明するので、心に響くのです。
出口:女性管理職比率についてはいかがでしょうか。
池松:女性管理職は、その手前の企画職上級(1・2級)の人財プールが4%未満と、絶対数が不足しています。企画職中級以下は15%程度いるのですが、年代としては30代後半でライフイベントが重なり、なかなか成果が出しづらい。もしくは評価の仕方によってそうなっているのかもしれません。また管理職は、顧客からBCPへの対応を求められるなど今の管理職の働き方を見ると、女性が昇格を躊躇してしまうこともあるのです。
出口:それは具体的にはどういうことですか。
池松:年初の能登地震もそうでしたが、たとえば震度5の地震が発生したら、1時間以内に状況を顧客に報告する義務があり、管理職がその責務を負う。そうしたら24時間、緊張してスマホを握っていなければいけない、と考えてしまうのです。お客様へのBCP対応は、総務、製造、資材などの社内関係者がお互いをフォローし代替えが効くように、女性だから男性だからということではなくて、人としてサスティナブルな働き方で対応できるように今、体制を作っています。
出口:管理職も周りのサポートありきでいいんだ、という本人・周囲へのメッセージになりますね。他にもダイバーシティに関する働きかけはありますか。
池松:2022年度の男性育休取得率は37.0%でした。私は4人子供がいて、2人目から育休を取得しましたし、総務部長の男性も合計3か月の育休を取得中です。役職者が育休を取得することで、性別を問わず多様な人財の働き方を会社が支援しているというメッセージになっていると思います。
「進化する人事」で次のステージを目指す
出口:アルプスアルパインの2023年度の年商は9,640億円でした。1兆円を伺うまでに成長した現在、池松さんが行っていきたい人事とはどのようなものですか。
池松:ビジネスには、2-3年先にゴールが見えるものもあれば、技術的な難易度が高くて赤字になるプロジェクトもある。ですから、エンゲージメントやパルスサーベイを見て、組織・個人の”個別の状況”に対応するのが人事の仕事なんです。従来のような“一律”は通用しません。人事になってみて、外から見ていたよりずっと大変だとわかりました(笑)。
楠田:では出口さん、最後のご質問をどうぞ。
出口:「人に賭ける」というフィロソフィーが創業時からあって、時代とともに受け継がれ進化していることに、大変感銘を受けました。将来的に、社員の皆様に対して人事としてどのようなサポートをしていきたいか、教えていただけますか。 池松:私個人としては、「2025年から3年間の中期計画を達成したら、社員の平均年収100万円アップ」という目標を立てても良いのではないか、と考えています。現状624万円の平均年収を3年間で5%ずつ上げたら722万円ですから、理論的には可能です。成果を出したら利益を社員に還元する仕組み、人事制度を作っていきたいと思います。
池松:私個人としては、「2025年から3年間の中期計画を達成したら、社員の平均年収100万円アップ」という目標を立てても良いのではないか、と考えています。現状624万円の平均年収を3年間で5%ずつ上げたら722万円ですから、理論的には可能です。成果を出したら利益を社員に還元する仕組み、人事制度を作っていきたいと思います。
楠田:エンゲージメント向上につながる施策で、新たなステージへの躍進が早期に実現することを期待しています。本日はありがとうございました。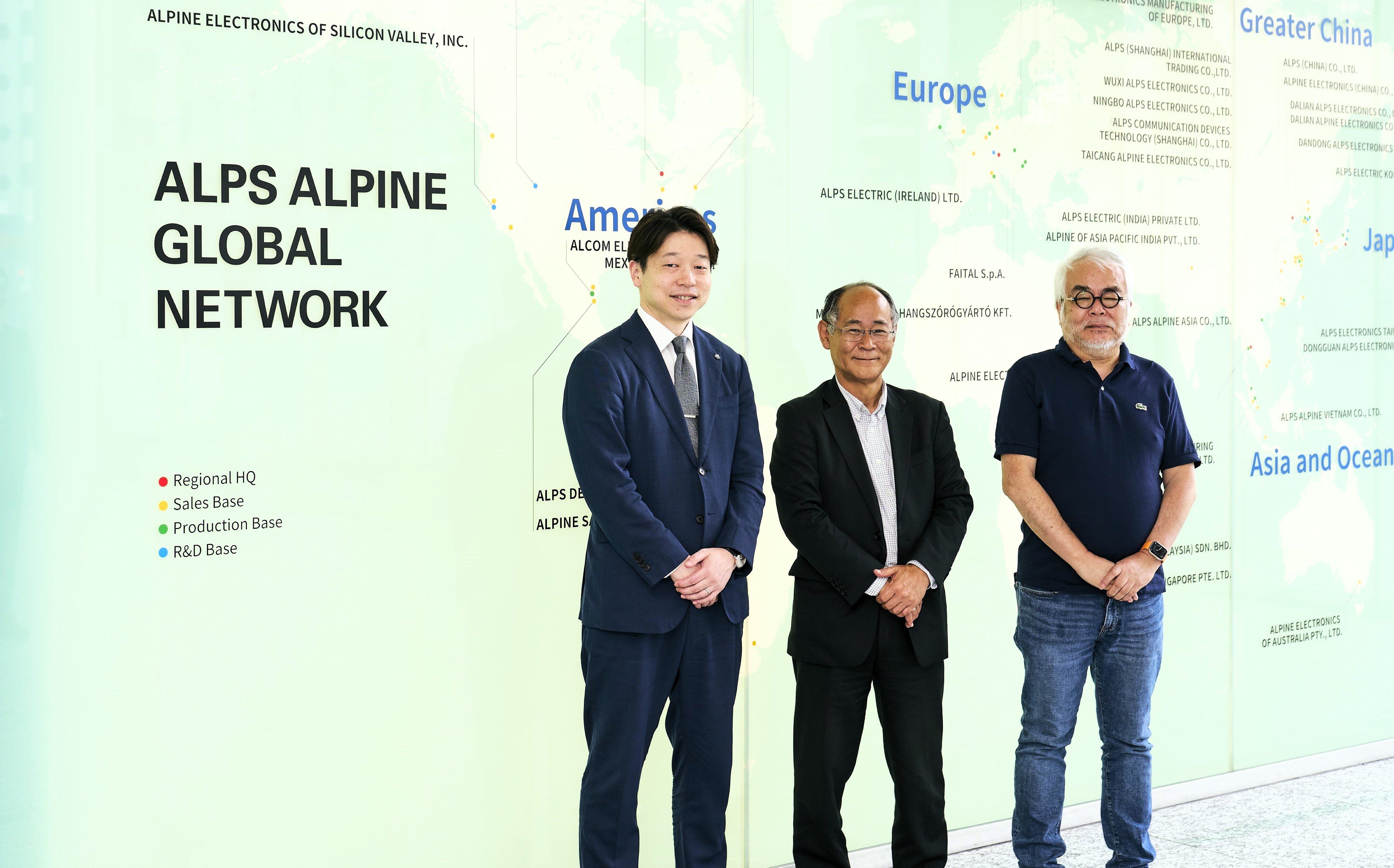 (キャプション) 左:出口亮輔氏 中:池松裕史氏 右:楠田祐氏
(キャプション) 左:出口亮輔氏 中:池松裕史氏 右:楠田祐氏
(執筆者:丸島 美奈子 / 写真提供者:武田 昌盛)
