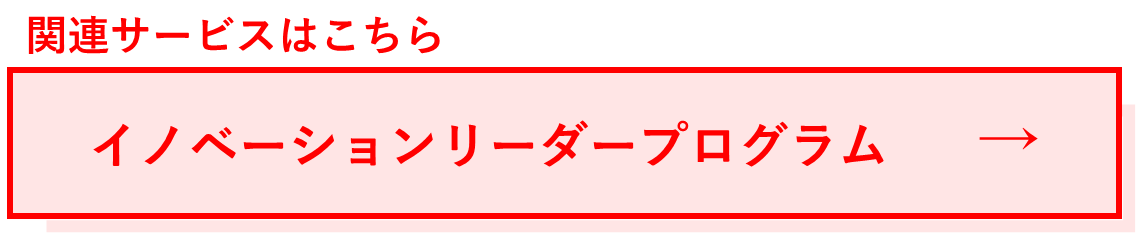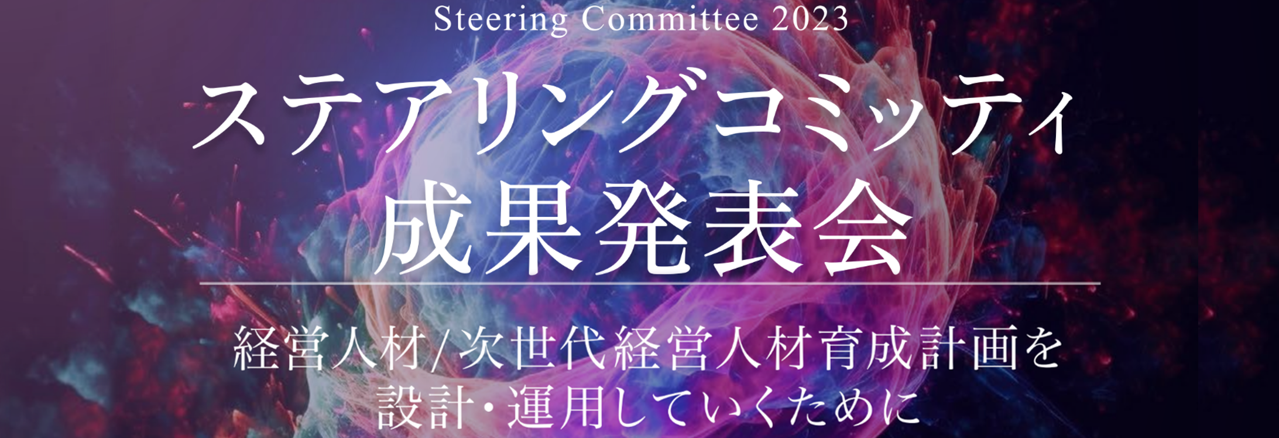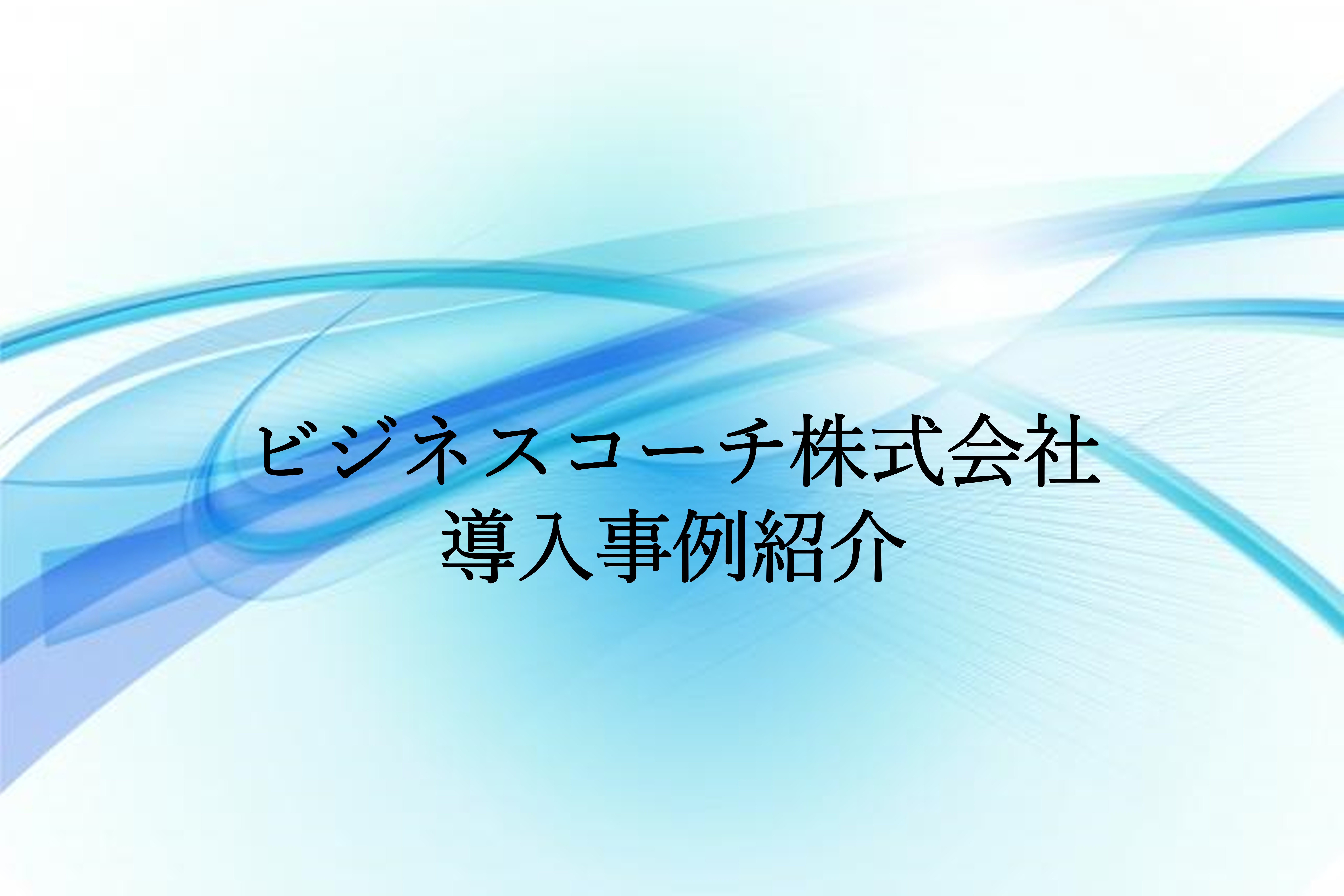- イノベーションリーダープログラム
アステラス製薬株式会社
(ビジネスモデル・キャンバス)
ビジネスモデル・キャンバスで新規事業創出のベースを確立

アステラス製薬株式会社
ビジネスモデル・キャンバスで新規事業創出のベースを確立
クライアント企業情報
アステラス製薬株式会社

アステラス製薬は、「先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献する」ことを経営理念に掲げ、研究開発型のグローバル製薬企業として積極的に事業展開しています。
2005年に山之内製薬と藤沢薬品工業が合併して設立されて以来、医療用医薬品に経営資源を集中させて事業展開してきましたが、社会の健康意識の高まりや多様化するニーズに対応すべく、新規事業創出に向けた積極的な検討を開始しています。
検討ツールとして「ビジネスモデル・キャンバス」を導入し、取り組みをスピードアップさせています。経営企画部で新規事業創出検討の責任者である武沢竜一氏に、取り組みの現状や今後の展開などについてうかがいました。
ご担当者様
武沢 竜一(たけざわ りゅういち)氏
経営企画部 次長 工学博士
1997年旧山之内製薬に入社。研究者として約15年創薬研究に携わったのち、2011年に経営企画部に異動。
ビジョンや経営計画策定を担当したのち、新規事業検討チームを率いて現在に至る。
お客様の課題・ご要望
- ・アステラスの新薬創出の強みと異業種の強みの融合
- ・新たな医療ソリューションの必要性を感じ、新規事業創出への取り組み強化
ビジネスコーチの提案・サポート
-
・河野龍太氏によるビジネス・モデルキャンバスワークショップとプレゼンアクションミーティング
自社の強みを生かしてニーズの多様化に対応
Q:貴社における新規事業への取り組みの現状や、これまでの経緯について、お教えください。
A:アステラス製薬誕生時に策定したVISION 2015で示した通り、当社はグローバル・カテゴリー・リーダーというビジネスモデルを選択し、グローバルな競争に挑み、成長してきた製薬会社です。
今後も我々のコアである新薬ビジネスは拡大していくのですが、疾患治療に限らず、予防や診断、治療後の再発防止など、医療全体のニーズが多様化してきているのも事実です。患者さんや医師にとどまらず、患者さんの家族、コメディカルを含む多くの医療従事者、病気にかかっていない健康な人など幅広いステークホルダーを対象とすることで様々な潜在ニーズが見えてくるのではないかと感じています。
さらに、ICT(情報通信技術)やエレクトロニクスをはじめとして、製薬業界以外の技術の急速な進歩により、そうした多様なニーズに応えられる可能性が高まってきています。アステラスの新薬創出で培ってきた強みと異業種の強みの融合により新たな医療ソリューションを真剣に考える必要性を感じ、ここ数年、新規事業創出検討に積極的に取り組むようになったのです。
検討チームを“共通言語”で強化
Q:2015年10月には、そのための検討チームもつくられたそうですね。
A:2015年10月以前も様々な検討を行っていましたが、ビジネス的な視点を加味した検討を強化する目的で、経営企画部内に検討メンバーを集めました。
Q:それに合わせて、「ビジネスモデル・キャンバス」も導入されていますね。
A:はい。検討メンバーは、研究部門から営業部門に至る様々なバックグランドを有しているので、融合することでいろいろなアイディアが出てくることは想像していましたが、それらを新たなビジネスに膨らませた経験者は少なく、議論のベースが定まらないのではないかとの不安がありました。
具体的に、どのようなビジネスモデルが考えられるのか?事業として、どれほどの可能性があるのか?アステラスの強みをどのように活用すべきか?そうしたことを的確に判断するための何らかの手段がなくてはいけないと考え、外部のいろいろなセミナーにも参加し、実際に体験してみました。
そして出会ったのが、「ビジネスモデル・キャンバス」です。当時一緒に検討していた他のメンバーも別のセミナーで体験したビジネスモデル・キャンバスの印象が良かったことや、イノベーションを創出し続けている様々なグローバル企業なども導入していることを知り、有用なツールになると確信しました。
Q:ビジネスモデル・キャンバスを有用と評価されたポイントは、どのようなところでしょう?
A:初期的アイディアを具体的なビジネスモデルに落とし込むためのポイントがクリアに整理されていてメンバー間の “共通言語”にできるところですね。メンバー全員が全体像を俯瞰できるようになり、共通理解が生まれるようになりました。
日本で唯一人の公認トレーナーが参画
Q:ビジネスモデル・キャンバスのプログラムはいろいろとあると思いますが、その中でビジネスコーチのプログラムを選ばれたのは、なぜでしょう?
A:日本で唯一人の公認トレーナーである多摩大学大学院教授の河野龍太先生に、ビジネスコーチのパートナーとして、ご指導いただけるというのが大きな理由の一つです。
単に外部セミナーなどでレクチャーを受けるだけでは不十分で、実際のビジネスモデルづくりや、その評価、検討案件の絞り込みなどを、チームに入っていただいて、実践的にご指導いただきたいと考えていたので、河野先生にぜひお願いしたいということになりました。
Q:導入してみて、その効果はいかがでしたか?
A:チーム発足当初から半年間、ご指導いただきました。ビジネスモデル・キャンバスを活用して、100件ほどのアイディアを10件程度に絞り込み、半年間の成果として、それらのビジネスモデルについて経営陣の前でプレゼンもしました。こうした実践的なトレーニングによって、検討メンバーのベースは確立できたと思っています。
既存部門を巻き込む「第3ステップ」へ
Q:その後、1年弱がたちましたが、取り組みの進捗はいかがでしょう?
A:新薬ビジネスに比較的近いアイディアからかなり遠いアイディアまで、さまざまな検討を行っています。アイディアごとに進捗スピードは異なりますが、新陳代謝も含めて着実に前進していますし、小さい成功も体験しつつあります。こうした具体的なプロジェクト推進を通してチームの経験値が確実に高まっています。
わたしは最初の半年が「第1ステップ」、次の1年ほどが「第2ステップ」で、いよいよ「第3ステップ」に差し掛かってきたと考えています。第1ステップでは、ビジネスモデル・キャンバスの導入などにより、ビジネスモデル検討のベースを学びました。第2ステップでは、チームが実践を通して経験値を高め、自立した専門集団になれたと思います。
そして、これからの第3ステップでは、社内の既存部門の支援を得ながらいかにスピード感を持って実行できるかが問われると思っています。大きなコアビジネスを持つ企業の中で新規事業を立ち上げるには、既存部門の理解や支援は不可欠であり、このステップにおける歩みを大事にしながら成功事例をつくっていきたいと考えています。
これからも社内の強力な支援者を地道に増やしていきながら、他社での新規事業立ち上げ経験者の成功事例や失敗事例を勉強して我々の活動にいかしていくことも重要だと考えています。ビジネスコーチには、そうした点のサポートもしていただければと期待しています。