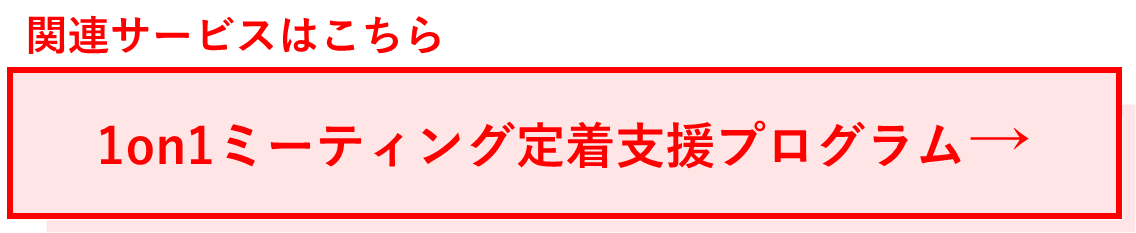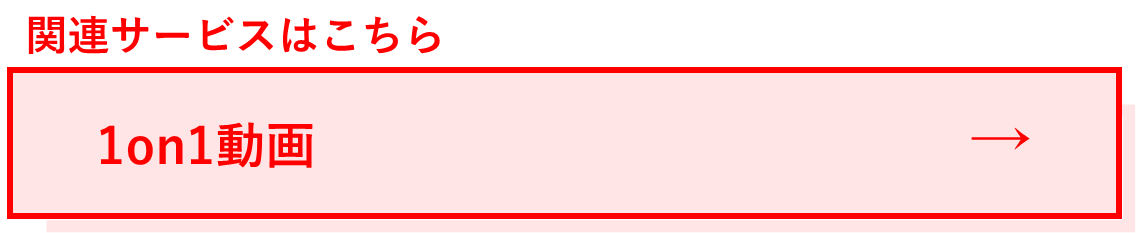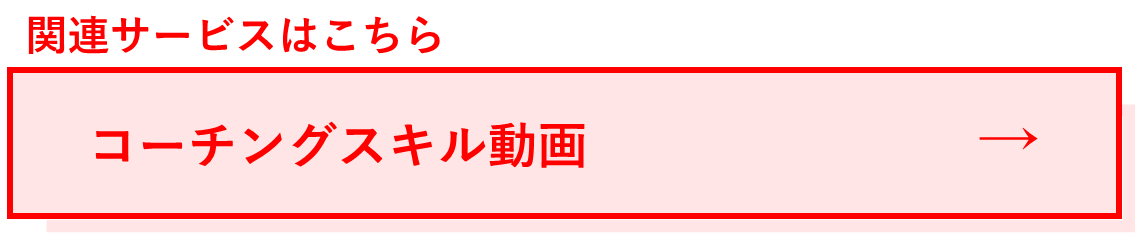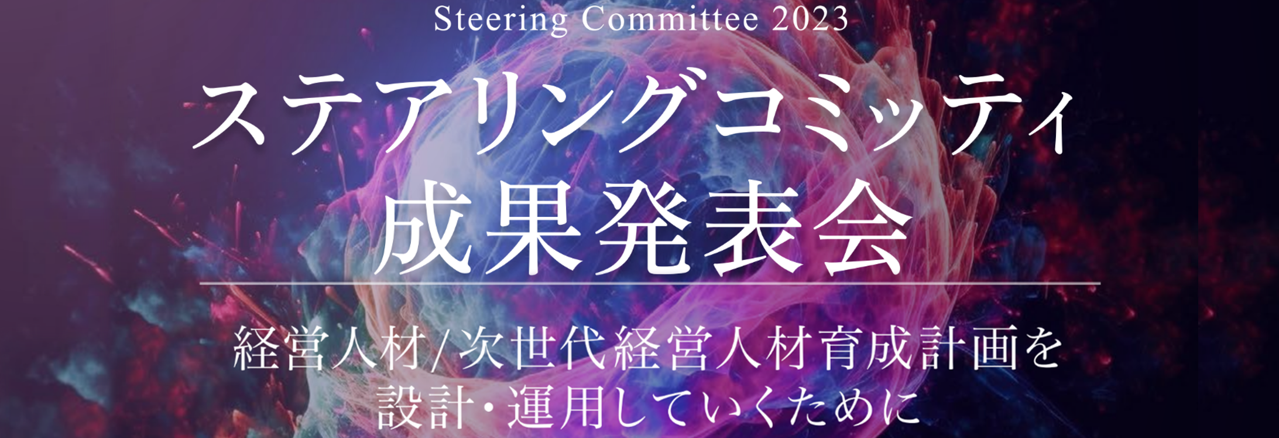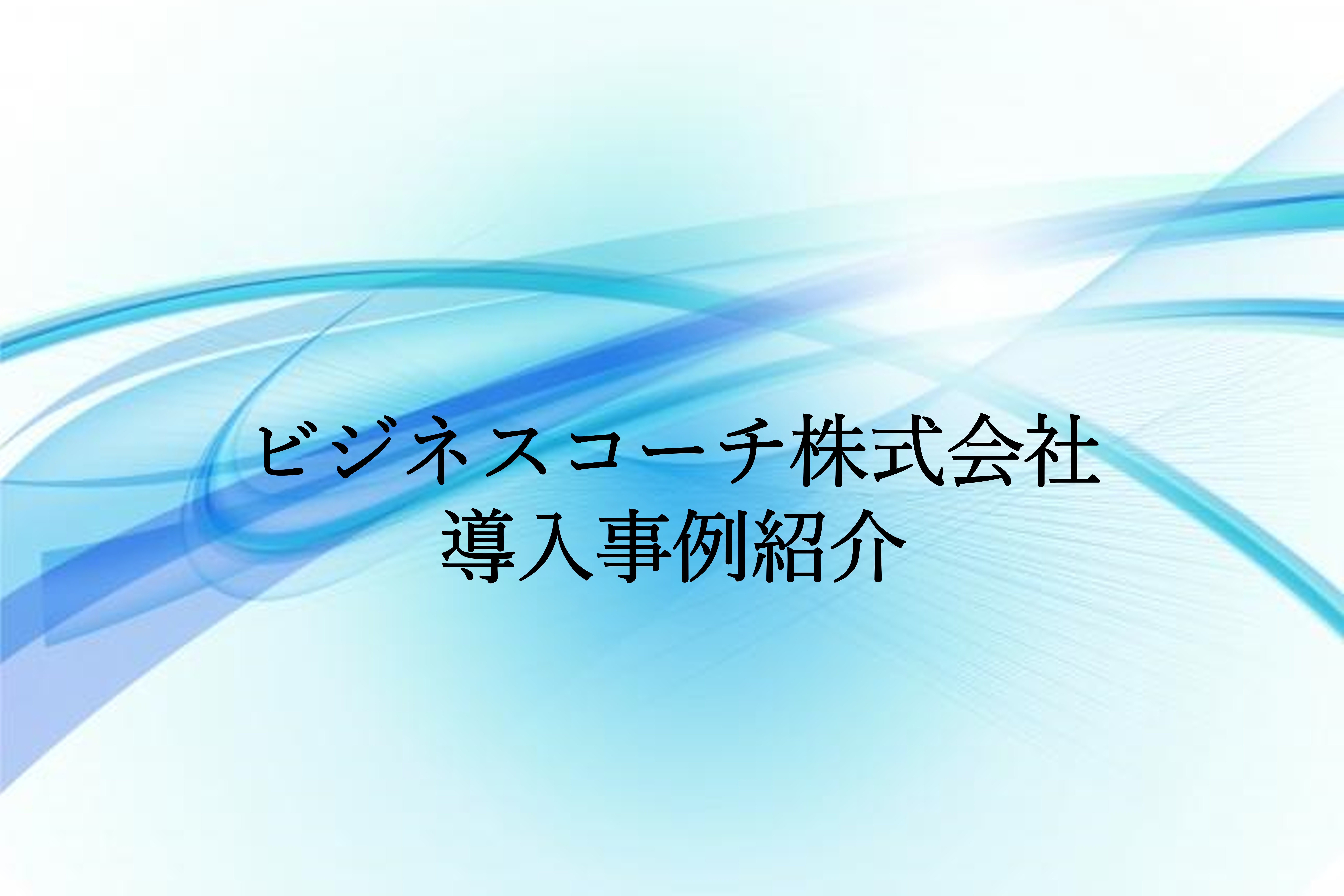- 1on1ミーティング定着支援プログラム
- 1on1動画
- コーチングスキル動画
株式会社荏原製作所
お客様に聞く(1on1導入プログラム) ー 株式会社荏原製作所 ー
「実践と失敗」から1on1を効果的に学び、上意下達のコミュニケーションスタイルを変える

1on1で上意下達のコミュニケーションスタイルを変える
クライアント企業情報
株式会社荏原製作所
1912年に創業。社会インフラや産業用装置、設備を設計・製造。グローバルに展開する産業機械メーカーとして、風水力事業、環境プラント事業、精密・電子事業を主要な事業としている。連結売上高5237億円(2020年12月末現在)。従業員数、連結1万7480名(2020年12月末現在)、単体4047名(2020年12月末現在)
ご担当者様
菅井 栄司 氏:
2001年新卒入社。風水力機械カンパニーにて国内公共ポンプ施設の設計などに約10年従事。労働組合の書記長を経て、2013年より人事グループ長や人事企画長を歴任し人事制度改革に携わる。2021年5月に業務革新統括部に異動し、現在は業務改革や働き方改革、生産現場の業務改善活動を推進。
堀江 拓生 氏:
2001年新卒入社。精密・電子事業カンパニーの技術部門や研究開発、経営管理、特許取得、人事、経理、本社経営企画室などを経験した後、2019年に中国での半導体関連新会社設立の責任者として赴任。2020年に帰国しグループ経営戦略・人事統括部へ。2021年5月より現職。
お客様の課題・ご要望
- 前例踏襲や現状維持の風土変革のためのコミュニケーション活性化
- 上意下達のコミュニケーションスタイルから対話型の組織の構築
- 1on1の浸透・定着によるエンゲージメントの向上
ビジネスコーチの提案・サポート
- 1on1研修(ガイダンス、スキル研修)
- 1on1動画、部下向け動画、オリジナル動画作成
1on1導入の背景:変革を望まない「企業風土」を変えられるか
――貴社では2020年5月よりビジネスコーチの1on1ミーティング導入プログラムを実施しています。なぜ1on1を導入したのでしょうか。

菅井氏:大きなきっかけは2019年に社長が交代したことです。新社長の浅見正男(取締役、代表執行役社長)や、精密・電子事業カンパニーのトップである戸川哲二(執行役、精密・電子事業カンパニープレジデント)は、当社の前例踏襲や現状維持の風土に危機感を持ち、コミュニケーション活性化のために1on1が必要だと認識していました。当時私は精密カンパニーの人事を担当しており、戸川から「社内に1on1文化を定着させたいので企画してほしい」と持ちかけられたのです。
――「前例踏襲」や「現状維持」の風土について、具体的に伺えますか。
堀江氏:当社は水やエネルギーの安定供給を支えたり、技術製造現場の安定稼働を実現したり、ごみ処理施設の建設・運営を担ったりと、社会のインフラに対して強い責任感が求められる事業を展開しています。部門による違いはありますが、事業の特性上、全体的に安全重視の気風が強く、前例踏襲や現状維持など、失敗を避けるための決断をどうしてもしてしまいがちな側面があったと認識しています。
菅井氏:組織内には、変革を望まない「企業風土」があるように感じました。部下の立場からすれば、横や斜めのつながりを持って変革を起こすよりも、上司をロールモデルと捉えてまっすぐ見ているほうが楽だったのかもしれません。
こうした状況を踏まえて、浅見や戸川はトップメッセージとして社員に「自発」を要求し、リーダーシップを持ったマネージャーの育成が必要だと発信していました。
――まずはマネジメント層から変わらなければならない、ということですね。
菅井氏:はい。当社では近年キャリア採用の割合が増えており、人材の多様化が進んでいます。加えて、2020年はコロナ禍の影響で在宅勤務をする社員が増えました。マネジメント層を中心として、コミュニケーションの新たなあり方を模索しなければならない時期が訪れていました。
コミュニケーションの課題:「上司から一方的に目標を伝えられるだけ」と訴える社員も
――従来、組織内ではどのようなコミュニケーションスタイルが取られていたのでしょうか。

堀江氏:基本的には上意下達のコミュニケーションスタイルでした。上司と部下の対話という意味では、MBO(目標管理制度)に基づく目標設定面談と期中レビュー、評価面談が中心。現在行っている1on1のように、自由なテーマで何でも話せる機会は全社的には設けていませんでした。
――そういった以前のコミュニケーションスタイルに課題を感じたエピソードはありますか?
菅井氏:私が人事制度改革を進めているときの印象的なエピソードがあります。
当社では2017年から組織の大型化を進めました。以前は部下のいないグループ長、いわゆる「名ばかり管理職」が多数存在していたため、組織を大型化・フラット化することで管理職の役割を適正化しようと考えたのです。
結果、「上司は本社にいるけど部下は地方拠点にいる」といったことが起きるようになりました。上司は地方拠点の部下のもとを定期的に回りますが、大勢の部下が複数拠点に在籍していることもあり、一人ひとりに十分な時間を割くことができません。
ある地方拠点の社員は「せっかく課長が来てくれて、話をしていても、課長は時計をちらちら見て時間ばかり気にしている」「一方的に目標を伝えられるだけで、こちらの話を聞いてくれない」と私たち人事に訴えてきたほどです。
――現場ではコミュニケーションに起因するさまざまな壁が生まれていたのですね。
菅井氏:経営側から要望されているだけでなく、人事としても、コミュニケーションのあり方を変えるために1on1文化を根づかせたいと強く感じましたね。ただ研修を行うのではなく、取り組みが陳腐化しないように、人事が事務局としてしっかり機能していくのだという決意を持って、1on1の導入に臨みました。
1on1導入のプロセス:失敗してもいいから、とにかく実践。「真剣に取り組むからこその悩み」が出てきた
――貴社ではどのような流れで1on1を導入していったのでしょうか。

堀江氏:当初、参加対象としたのは部長クラス約30名、課長クラス約100名です。まずは役員向けのガイダンスを行い、その後は部課長向けに1on1の意義を伝えるガイダンスとスキルトレーニングを実施していきました。
研修コンテンツについてはビジネスコーチと相談しながら、まずは最低限の基本スキルを学ぶために導入ガイダンスを実施、最初の研修後に「早速明日から実践してください」と伝えました。
菅井氏:「最初は失敗してもいいから、とにかく実践してみてください」とお願いしたんです。3ヶ月後に参加者へアンケートを取り、実践の中で感じた課題の解決法を学ぶためにスキルトレーニングを受けてもらうという流れにしました。
――スキルを固めてから実践していくのではなく、まずは実践し、経験から学んでいくということですね。
堀江氏:はい。最初の研修で学ぶのは本当に基礎的な部分だけです。「コーチング」や「傾聴」など、応用編といえるスキルについては、実践における失敗を踏まえたほうが効果的に学べるのではないかと考えました。
菅井氏:うれしかったのはマネジメント層が失敗を恐れず実際に動いてくれたことですね。現場でどんどん実践し、研修の中でも真剣に取り組んでくれました。それは研修開始後にマネジメント層から寄せられる相談内容からも見て取れます。
「私は部下が30人いるから、2週間に1回の1on1はできない」「じっくり話せる場所を確保したいけど、会議室の予約がなかなか取れない」など、真剣にやってくれているからこその悩みがどんどん出てきたのです。
こうした相談に応じながら、「在宅勤務のときにはオンラインで実施してみませんか?」「空いている時間帯に食堂を使って1on1をやりませんか?」など、人事からもさまざまな方法を提案していきました。
1on1導入の効果:エンゲージメントサーベイの結果、「直属の上司」に関する数値が上昇。部下側からの「新たな悩み」も
――1on1を導入してから現在まで、定量面・定性面でどのような効果が見られていますか。

菅井氏:定量面については、2019年から当社はエンゲージメントサーベイを行っており、今年で3回目となります。この中に「直属の上司」について聞くカテゴリーがあり、部下から見て「キャリアプランを示してくれる」「ほめてくれる」「アドバイスをくれる」などのスコアが有意に上昇しました。
堀江氏:定性面については、現場の空気にも変化が表れていると感じます。私自身が長く身を置いていた精密・電子事業カンパニーの例では、半導体関連事業はトレンドの移り変わりが早く、お客さまからもさまざまな要望が寄せられるため、現場はとても多忙です。
新たな取り組みを提案すると、提案した人自身の業務負荷が高まってしまうこともあって、従来は「言った者負け」の雰囲気がある状況でした。それが、1on1の場が設けられ、一人ひとりが感じる課題を部署全体で解決していこうとする動きが生まれたことで、「新しい提案を出していいんだ」という空気に変わってきています。
菅井氏:部下側の動きも変わってきていますね。人事では全国約700人の旧一般職社員(※)を対象とした「E-volution研修」を実施しました。このプログラムではMBOにおける目標設定の立て方やキャリアプランを学ぶ内容があり、そのための事前課題として「課長とMBO面談をした上で研修に参加する」ことを求めたのです。
(※)2018年人事制度改定により一般職を廃止し、総合職と統合。
結果、9割以上の参加者が上司と面談をした上で研修に臨んでくれました。これも1on1が定着しつつあることの表れだと感じています。
――プログラムを実施したことによって見えてきた新たな課題や改善点があればお聞かせください。
菅井氏:部下側からは「1on1の時間をどのように活用すればいいか分からない」「何を話せばいいか分からない」という悩みも寄せられるようになりました。
そこで現在は、社内アンケート調査の結果を踏まえ、「1on1の好事例集」を集めた当社オリジナルの動画コンテンツを発信しています。心に抱えていた悩みを上司にどのように打ち明けたのか。上司はそうした悩みをじっくり聞くためにどのような1on1を行っているのか。そんな実践ノウハウが伝わるように制作しています。
堀江氏:上司側だけでなく、部下側へも示唆する必要があるんですよね。ただ1on1を実施するだけでは、部下は遠慮して本音を話せないこともあります。「話すテーマが特にない……」と迷っている状態は、まだ心理的安全性が確保されていない状態だとも言えるでしょう。だからこそ、1on1を行う上司だけでなく、受ける側の部下もフォローしていく必要があると思っています。

直属の上司以外とも1on1を行い、新しい視点を得ていきたい
――今回、1on1文化を定着させるためのパートナーとして、ビジネスコーチを選んだ理由をお聞かせください。
菅井氏:検討段階では複数社からご提案をいただきました。その中でビジネスコーチを選んだのは、コロナ禍の状況にあって、オンラインで研修を進めるノウハウをどの企業よりも提供してくれたからです。人事としては1on1にとどまらず、研修運営のノウハウという点でも学べる良い機会になると考えていました。結果的に、オンライン研修の参加者からは高評価でしたね。
堀江氏:ビジネスコーチは当社の状況をしっかり理解した上でプログラムを準備してくれていると感じます。参加者の満足度が高いのは、緻密な研修設計の賜物でしょう。私たちの話を親身になって聞いてくれて、1on1を陳腐化させないための効果的な研修を提案してもらっています。
菅井氏:「トップを巻き込んだほうがいい」とアドバイスをしてもらったことも大きかったですね。それをきっかけに、各カンパニーのプレジデントと事業部長・統括部長が集まる「エグゼクティブ・ガイダンス」と名づけた場を用意し、1on1導入に向けた機運を盛り上げていくことができました。
また、2020年4月に1on1導入を検討し、わずか1ヶ月で導入を始められたことも、トップの巻き込みを進言してくれたビジネスコーチのおかげです。
――ありがとうございます。今後の展望や、ご予定されている施策・取り組みについても教えてください。
菅井氏:直近のテーマは何よりも「1on1を風化させない」ことです。定着にはまだまだ時間がかかると思いますが、地道に取り組み、人事が社員に伴走し続けることが大切ですね。
堀江氏:1on1の効果を広げていくという意味では、工夫の余地がまだまだあると思います。現在はカンパニーごとに実施していますが、今後はカンパニーの壁を超えて、同職種で課題を共有し合うような場を設けたいですね。
菅井氏:普段は接点がない人同士の1on1もたしかに有効だと思います。直属の上司以外の人とも1on1を積極的に行い、新しい視点を得ていくことは、企業風土を変えていく上でも重要でしょう。1on1文化を通じて、今後もコミュニケーションの活性化を全社的に進めていきたいですね。

その他弊社サービスの詳細については、ページ上部の「サービス」タブより各項目を選択のうえご確認ください。
個別のご相談をご希望の方は、下記お問い合わせフォームもぜひご活用ください。